1974年5月、我々は広福寺住職の好意で15aの伊予柑園を貸してもらい、有機農業の研究園を作り、これを「無茶々園」と名付けた。
muchacha(ムチャチャ)はスペイン語で、本国ではお嬢さん、メキシコではねエちゃん、フィリピンでは女中といった意味の砕けた言葉だそうだ。ネオン街の蝶を追っ掛けるよりみかん畑のアゲハチョウでも追っ掛けようや、無農薬無化学肥料栽培なんて無茶なことかもしれないが、そこは無欲になって、無茶苦茶に苦を除いて頑張ってみよう、という意味を含めて「無茶々園」と命名した。
最初の数年間は実験段階であったといえる。1975年に伊予市で自然農法を実践している福岡正信師匠の園を見せてもらい、師の指導を受けて実験園の無農薬・無化学肥料栽培を開始した。この年に収穫した伊予柑は一般流通で出荷したため外観が悪く大半が加工となった。
3年目になってようやく有機農業、自然農法という言葉が理解できるようになったが、まだ無農薬無化学肥料でやっていける見通しはなかった。無茶々園の農業に対する考え方が大筋でまとまりかけたのは実験園を作ってから数年が経った頃だった。みかん専業の経営だが、収入の上がる品種に更新していくだけでは経済の大きな変動にはついていけない。農業を主体に海と山と段々畑を有機的にサイクルさせる町内複合経営が理想であり、できるだけ石油には頼らないようにしようとする方向がまとまった。山のクヌギを切って椎茸の菌を打ち、長野県から日本ザーネン種の山羊を10頭買い入れ複合経営の実験を始めた。しかし、組織的、精神的未熟さでこういった実験は挫折してしまった。
有機農業を成功させるには、できた生産物をそれなりの価値で食べて貰うことが必要である。1977年の伊予柑は松山市の自然食品店に引き取ってもらい、初めて無茶々園としての期待の値段が付いた。この店との出会いから、理想の農業に近付くためには農業の問題から出発して、食生活、健康、社会環境、教育に至るまで考える必要があることを教わった。そのためにも無茶々園の運動は単なる農産物の生産方法の問題ではなく、まちづくり的な活動に広げていかなければならないと理解した。1978年には愛媛新聞、朝日新聞、NHKなどのマスコミが無茶々園を取り上げ、無茶々園は一躍全国に知れることとなった。そのおかげで多くの理解者、指導者を得ることができ、名実ともに無茶々園は動き始めた。この年のみかんは全国の皆様に注文いただいて全量を販売することができ、当初最大の問題であった販売面にも期待が持てるようになったのだ。




柑橘生産者
無茶々園の名つけ親斎藤 達文
続いてきた要因は
周りから育てられたこと
無茶々園がここまで続いてきた一番の要因は周りから育てられたこと。
交流を重ね、いろいろな人を紹介してもらい、いろいろと教えてもらえた。無茶々園を始めたのは28歳の頃。26歳で明浜に戻り慣行栽培で柑橘を作っていたが、後継者が集まってお寺の畑を借りることになった。まだいまのような組織にはなっておらず、後継者が集まってワイワイ騒ぐような場所だった。そんななか研修で福岡正信さんに出会った。まだ有機農業という言葉もない時代。福岡さんのことが好きだったのだろうな。影響を受けて自分達も無農薬で作るようになった。
そうこうしているうちに報道機関が来るようになった。反環境汚染が広まりだして有機のものを欲しがる消費者も増えていたから有名になった。そして横のつながりが増えて情報が広がった。東京に勉強会に行き、市場などにも行き、この人に会いなさいと紹介されていろいろな人に会った。販売先も増えていった。だから販売に苦労したというような思いはない。販売先が増えたら作る量も増やさなければいけない。自分たちの畑でも有機で作るようになった。しかし、化学肥料をやめて1年目で葉っぱの色が変わって木の育ちが悪くなった。そこで自分たちの有機の肥料を作らないけない、となった。販売には苦労しなかったが生産や数量調整は大変だった。
片山元治はスポークスマン。外への発信力はあった。けれどもそれ以上に職員や地域の生産者など周りで支える者がいたからいまの無茶々園がある。理事会で片山が東京から得てきた知識を話す、それを受け入れられる母体があったことで無茶々園は成長できた。
いま自分で経営しているみかん作りでは園地を拡大している。外国人の実習生を3人入れているが、みかん作りに特別な経営能力がいるわけではない。山へ行くのが好きならだれにでもできる。先輩が骨折ってこの地に作ってくれた園地を荒らしたくない。年を取ったら足腰は弱ってくるが、まだまだがむしゃらにやらなければいけない。

柑橘生産者宇都宮 氏康
無茶々園に入って何より楽しかった
無茶々園には創業から少し経ってから加入した。創業メンバーと仲が良かったからオブザーバーのような形で会合に参加していた。彼らと話していて楽しかった。オーラ、熱はすごかった。今の若手にも見せたいと思う。
当時はスプリンクラーのような施設もなく、年に10回以上、手作業で農薬を撒いていた。こんなこと一生はできないという思いも持っていたが、「複合汚染」を読んで彼らの話が腑に落ちた。そして無茶々園に入った。無茶々園に入って豊かな気持ちになった。何より楽しかった。化学農薬を使わなくなって体調も良くなった。消費者との交流も楽しかった。みかんと一緒に入れた葉書で返事が来るのがとても嬉しかった。
1992年から天歩に「虹の里へ」というタイトルでコラムを書かせてもらった。発行する方は大変だったかもしれないが、これは自分の勉強にもなった。書くためには、テーマを考え、新聞を読んだり、本を読んだり、人に話を聞いたりして勉強しなければいけない。それが地域のことを考えるきっかけになった。
明浜は立地条件からすでに価値がある。あるとき、ここの母ちゃん連中は世界に通用する、と外から来た人に言われたことがある。特別な何かをしたわけではない。普段の生活を見てもらっただけ。何の変哲もない普段のことを話す、それが価値だと思う。都会の人が喜んでくれるのはすごいこと。ここには人間の原点がある。自分達自身の価値に気付かなければいけない。無茶々園、明浜は豊かな暮らし方のモデルとして発信していけるところだと思っている。




柑橘生産者
大津敬雄
川越文憲
自分たちは創業者に使われた世代(笑)
自分たちは創業者に使われた世代(笑)。はじめは狩江地区の農家後継者でも若いほうで、まだ試験園だった無茶々園を手伝ったことがきっかけだった。そして斉藤達文さんから誘われて一部の園地で加入した。無茶々園の栽培方法で作ったらみかんの糖度が上がり、ちょうど父親から自分たちに代替わりしたころだったから、そのうちに全園地の加入を決めた。
苦労したこともたくさんあった。はじめの頃は青果として出荷できずに販売先がなく、収穫したものを捨てたこともあった。浮き皮でみかんをコンテナ300杯以上を捨てたこともあった。ならば自分たちでジュースをと、搾汁設備を借りて作ってもみた。指導を受けながら作ってみたものの、加熱温度が足りず中身が発酵して爆発したものもあった。
片山元治さんは責任者をつけず構想状態で走り出し、柑橘以外にもいろいろなものを手掛けていった。椎茸から始まって、フルーツランドと称して農道も通ってない山にリンゴ、ヤマモモ、銀杏などを植えた。園地で飼いはじめたヤギがみかんの葉を食べ尽したりもした。設備にもいろいろ投資したけれども、結局ほとんど使わなかったものは数えきれないぐらいある。
当初は販売から搬送まですべて自分たちでやっていた。車で東京までジュースを運んだり、当時の神田市場練塀寮に泊まって、電話番号と住所だけを頼りに客先を回ったり、生協の配送トラックに乗せてもらったり。東京でみかんを販売していたら個人消費者の方に声をかけられたこともあった。今の若手も、遠回りしながらでも消費者と触れ合う場に参加したり、いろんなことに挑戦してほしい。

柑橘生産者
てんぽ屋片山 恵子
始めた当初は何でも自分達でこなした
自分自身も合成洗剤でなく石鹸を使いたい、添加物を使いたくないという思いがあって、夫の片山元治と一緒に無茶々園を始めました。
始めた当初は何でも自分達で。社員もおらず農家が集まって家事をしながら電話をとったり事務仕事をこなしていました。当時の運送手段は鉄道便。収穫した後、自分たちで荷造りをして隣町の駅まで持って行き発送。そうしたら15kg箱で1日40箱を作るのが精いっぱい。でも、それをわざわざ駅まで取りに行き、配って広めてくれる人、カメムシの被害を受けても買い支えてくれる人がいたことがとても嬉しかったんですよ。
生産者の奥さんが集まってできたのが「なんな会」でした。資金稼ぎにちりめんを小分けして販売することから始まりました。なんな会で消費者の方と話しているとき、石鹸を使おうというのは男性が勧めても説得力がないと感じたのです。私たちが石鹸運動について語れるようになろう、そのためには勉強会をしようとなりました。始めのうちは興味のない人が多かったのですが、消費者とつながるうちに興味を持つ人も増えていきました。
消費者の方のなかにもさまざまなエキスパートがいました。石鹸運動だけでなく、ジュースや牛乳の低温殺菌など、勉強会を開き消費者の方からいろいろ教えてもらいました。そして来てくれるお客様にどういう食事を出せばいいか、とまた勉強会を実施する。そんな習慣ができたんです。
なんな会自体は、働きに出るなど農業に関わる女性が減って行われなくなってしまいました。でも、そういった勉強会を実施してきたことが後々のヘルパー講座、ひいては地域介護のレベルアップに繋がっていったのではないかと思います。





ちりめん漁師(祇園丸)佐藤 吉彦
責任を持って地域づくりに取り組む
無茶々園と言えばみかんだが、なぜちりめんを扱っているのかと聞かれることがある。みかんやちりめんに限らず、地域を活性化させたい思いのある人はどんどん入ってほしいと思っている。
明浜に戻ってきたのが25歳の時。その前はコンピューター修理の仕事。漁業の仕事は28歳の頃からはじめた。無茶々園へ加入した当時、首都圏コープ(パルシステム)に研修に行ったとき、顧客拡大の車に乗って一緒に家々を回ったけど、ほとんどがドアも開けてくれない。そんななかでも、自分が作ったものでもないのに熱心に売ってくれる人がいることに感激した。そして東京の大田市場を見て一日に販売される量の多さを見て驚き、販売や流通の仕組みは変わっていくと感じた。そして明浜に戻ってすぐ自分で販売するための準備を始め。
加入前から無茶々園のことが好きだった。LPG基地反対運動で、無茶々園の「基地に反対する以上は責任を持って地域づくりに取り組まなければならない」という考えに共感して、参加したいと思っていた。無茶々園では環境活動ができるのが面白い。それまではあまり考えたことがなかったけれど、昔からこの地域は先人が魚付保安林を整えて海の環境を守ってきたことにも気が付き、活動に取り組むようになった。
無茶々園で外から来たお客さんを船に乗せて説明する機会ができたことで、自分もいろいろなことを考えられるようになれた。一度限りなら適当なことが言える。けど2年、3年と続けて来る人もいる。そんな人には違う話をしたいと思い、ついホラを吹く。そうするとその責任を取らなければいけなくなる。2回目に来た人から、新しい話が聞けて良かったと手紙をもらうことがある。それを見たらもっと努力しようと改めて思うのだ。
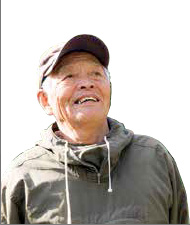
柑橘生産者宇都宮 利治
地域の活気もあり、秋祭りもできる
加入する前までは農協で農薬を使うよう指導していた立場だったので、無茶々園の存在には少し困っていた。しかし、斉藤達文や片山元治は地域のリーダーとして活躍をはじめていて、地域の中心になる者と一緒にやっていきたいという思いや、彼らのリーダーシップに魅かれて無茶々園に加入を決めた。
無茶々園に入って良かったと思う。作ったものを全量取ってくれる。無茶々園に加入していなかったらいまごろ農業はやめていただろう。おかげで地域の活気もあり、秋祭りもできる。もう一つ無茶々園の良いところは消費者と交流できること。メッセージや葉書を返してくれるのが励みになる。葉書は全部保管している。南予用水・スプリンクラー施設が竣工したのが1994年。その年の暮れまで町議をしていた。当時、公的にはスプリンクラーで水も農薬も撒くことで農作業が楽になると言って進めていた。しかし無茶々園の組合員も増えている頃で、農薬散布をやるかどうかで議論になった。結局スプリンクラーは灌水だけの利用となって、農薬防除の作業が楽になること望んでいた側からは大きな反発が起きた。それで農薬を撒かない代わりに、無茶々園が潅水施設の償還金を払うことになった。一時無茶々園の組合員の負担はかなり増えたが、結果として組合員の数も増えた。従来のやり方を変えても良いと思っていた人も多かったのだろう。
幸い2004年以降は大きな台風被害がない。今が増やしどき、千載一遇の好機。若手が勉強に来れば、できるだけ自分のわかっていることは伝えていきたい。耳で教わるだけではなく山で実践して欲しい。無茶々園の会員としてやる以上、みかんで食べていく百姓としての意識を高く持ってほしい。





柑橘生産者 / 代表理事
西予市議会議員宇都宮 俊文
幅広い意味での仲間づくり
農事組合法人無茶々園の会長になったのが1998年。会社としての職員が増えてきたころだった。その前にはスプリンクラーでの農薬散布を止め、地域にも迷惑をかけた。それは頭に入れておかなければならない。一般栽培の人たちにも意見がある。地域の農業は自分たちだけでやるものではない。しかし、止めていなかったらいまの無茶々園はなかっただろう。
2004年の台風被害は、個人的に車や倉庫にといろいろ投資したタイミングだったため大変だった。無茶々園全体でも樹が枯れ売上も大きく減って、かなりの面積を改植することになった。それでも嘆いてばかりではいられなかった。農業とはこういうもの。何の事業をやっても投資は大事。腹を据えてやらなければいけないと思ってやってきた。
大変なことも多くあったけれども仲間も増えた。しかし、人が増えただけ組織の底辺を上げていかなければいけない。放任と有機栽培は違う。自分たちだけの土地ではない。また、人とは違うことを続けなければいけない。自分たちの個性を持ちながらも、ある程度謙虚さは必要だと意識し続けてきた。生協の交流会に出たら、何百という生産者がいるなかで目立たなければ、と話し方を考えてきた。都会に行ったときも方言で話す。そのほうが興味を持ってもらえる。田舎は何もないと嘆く人もいるが、何もないことも宣伝になる。劣等感を感じるのではなく、自慢すべきことだ。
家族で楽しく仕事をして飯が食えたらそれが一番だが、田舎で雇用を増やすことも必要だ。これからも幅広い意味での仲間づくりを続けていきたい。

ファーマーズユニオン
天歩塾村上 尚樹
どう働くか、ではなく、どう生きていくか
続けていくことが大事。これは先輩から教わったことです。自分たちだけではなく、創業者はじめ先人が続けてきたからこそ、いまの仕事や生活があります。無茶々園で働き始め10年以上経ちましたが、基本的には失敗ばかりです。その失敗を繰り返さないようにして続けていくことが大事だと思っています。
初めて無茶々園に来たのは2004年。大学4年生の時に農業や田舎暮らしの好奇心から研修で来園しました。研修に来るまではどう働くかを考えていましたが、無茶々園で研修していくなかでどう生きていくかに変わりました。生き方としての農業。農家やその時のファーマーズユニオン天歩塾の先輩が格好良く見えたのです。農業はやりがいのある仕事。ただどの作物を作りたいかではなく、何が求められているかが大事だと感じていました。
しかし、やはり生業としての農業は大変でした。働き始めて間もない頃、一緒に働く気持ちがあり、自分も共に仕事をしたいと思った人がいました。しかし、そのころは新たに人を雇う余裕がありませんでした。楽しく仕事をする、幸せな生活を送るということは自分だけでは完結しない。人を集めなければならない。そのためには事業として成立させなければならない、と気が付き、農場を黒字にして自立した組織にしたいと働いてきました。変わらないことや過去へのリスペクトを持ちつつも、変えなくてはならないこともあります。変わらないために変えることも必要だと思います。
ファーマーズユニオン天歩塾は家族農業とは違う新しい農業を目指しています。先人たちがいたからこそ、続けてきたからこそ、いまがある。農業は継承産業だと言われます。親子で代々続け、一年一年の積み重ねが成果を生む。それに対し、最初は何の知識も技術もない人間でも農業ができる仕組みを模索していきたいと思っています。地域の生活を尊重しつつ、こんな生き方もあるということを提示していきたい、伝えたい。そして人を増やして地域を盛り上げていきたいです。




株式会社地域法人
無茶々園西原 和俊
年々いろいろなものが増えていく
無茶々園に入社したのは2000年の12月。そのときはファーマーズユニオン天歩塾に所属していました。はじめのうちは言われたことをやっていただけでした。いま、宇和選果場の責任者となり、四国エコネットの総会の段取りをしたりするなかで、無茶々園の歴史や思いなども理解できるようになりました。
入社したのはちょうど年々いろいろなものが増えていく時期でした。取り扱う品種や商品だけでなく、スタッフ、生産者や取引先などの関わっている人たちも増え続けていきました。そのなかで担当者として無茶々園の業務が円滑に流れていくように努めてきました。
出荷は期限が決まっていることです。出荷する品種・商品や発送先が次々と増えていくなかで、実際の出荷を行っていくのは大変なことでした。裏方の仕事であり、いまでも苦労しています。でも、それが自分の性に合っているのかもしれません。業務のなかで、無茶々園のことが自分のことのように考えられるようになっていきました。
yaetocoは順調に伸びていて、出荷していてもそれが実感できて楽しく思います。四国エコネットの生産者も古い人は10年ぐらいになりました。明浜も明浜町外もそれぞれの地域独特の雰囲気はありますが、生産者としてはみんな同じだと思います。
業務はどうしても販売や生産者から引き受ける仕事が多くなってしまいますが、これからはこちらから発信していきたいです。そして業務の仕事を通じてこの広がりを伝えていきたいと思います。

株式会社百笑一輝前田 寛明
本格的な福祉事業に取り掛かった
東京で働いている頃に、五感で感じる有機農業に興味を持ち、働きながら援農をしていて紹介されたのが無茶々園でした。ファーマーズユニオンのスタッフとなった後、事務所で出荷や交流の仕事をしていたころ、ヘルパー2級講座を開講することとなり、運営をしながら自らも受講しました。
その後、配食サービス「てんぽ屋」を始めた生産者の奥さん達と一緒に、家に引きこもりがちの高齢者のために「いきいきさろん」を開催。近くに住んでいてもなかなか普段は顔を合わせない方々がゆっくり話す機会ができて喜ばれていました。そんななか、家族介護だけでは難しい高齢者や独居の高齢者が増えたこと、働く場所を作り暮らしが成り立つようにしなければの思いから本格的な福祉事業に取り掛かり、株式会社百笑一輝を2013年5月に設立。この社名には「100歳で笑顔が絶えず、人生の完成期を輝いて過ごしてほしい。百姓は100の仕事をしながら自立する事業者。」との思いを表現しています。
福祉サービスの展開には事業化が必要で、まずデイサービス・有料老人ホームの施設を建設することとなりました。とにかくはじめてのことで、いろんな方々と相談しながら2014年2月に「めぐみの里」を開所することができました。会社の理念を職員みんなで話し合って決めたり、仕事のシミュレーションをしたりと、一体感をもって良い施設にしようとアイディアを出し合いながら頑張れたことはかけがえのない経験でした。
2015年11月には地域のさらなる要望に応えるため「海里(みさと)」を開所し、職員数は35名ほどとなりました。「共に生きる・共に働く・自宅で最期を迎える」を目指し、気軽に困りごとを相談できる居場所づくり、あらゆる世代、あらゆる境遇にある方を巻き込んだ福祉拠点づくりを推進していきたいと思います。
※この内容は2017年4月時点のものです。